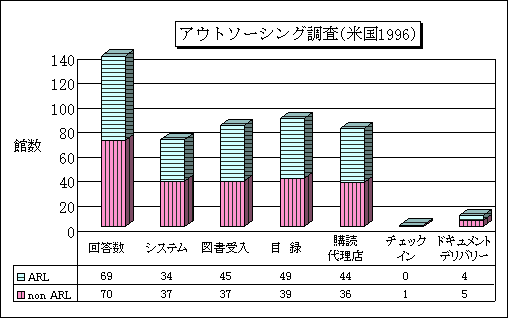
はじめに
1.図書館の将来展望
1−1.発想の転換
1−2.ハイブリッド図書館に向けて
1)高度化 2)効率化 3)共生化 4)グローバル化
2.電算化・EDI・アウトソーシング
2−1.電算化等の状況 【原稿からはカット】
2−2.電算化による改善・改悪 【原稿からはカット】
3.雑誌業務改善
3−1.一括納入方式による雑誌業務の改善
3−2.一括納入方式への疑問 【原稿からは一部をカット】
3−3.代理店によるEDIサービス 【原稿からはカット】
3−3.電子雑誌の可能性
3−4.雑誌係による改善
おわりに:人材育成、大学改革との関連性
参考文献
近年、図書館が業務改善を必要とする理由は6つである。
・「予算の逼迫」により、高度成長期の時代に行われていた従来型のサービス方針が維持できなくなってきた。
・「新しいサービス対象の出現(利用者の多様化、利用動向の多様化、電子媒体)」により、新しい業務を追加するか、従来の業務を再構築する必要が出てきた。
・「外圧(社会、文部省、大学当局)」により、図書館の都合とは関係なく業務改善に取り組まざるを得なくなってきた。◆1)-4)
・時代の求める意識改革を完了した「やる気のある図書館員の出現」がある。◆5)
・新館建築、電算化、そのバージョンアップを契機に「図書館自体の覚醒」があった。◆6)
本稿では、まず図書館における業務改善の概要を述べ、、その後で筆者の担当している雑誌業務の再構築について取り上げる。
・改善の効果は何か:時間と費用の節約、図書館サービスの向上・多様化が業務改善の効果となる。
・改善には何をなすべきか:開館時間の延長、休日開館、係間の調整と業者との協力によって資料提供を短縮など、利用者アクセスの向上。利用者の生産性を向上させるための図書館環境の向上と館員のサーポート。
また、資料の収集・提供は手段であり、「学生を育てる」という大学と共通の目的のために、大学との協力関係を構築することも重要である。図書館の目的を狭義に解釈しないで、広義に解釈したうえで、業務改善に取り組まなければ、大学当局の理解を得ることはおぼつかない。これには、自己目的化された旧態依然とした図書館のサービス概念からの脱却が鍵となるだろう。
(株)トヨタは、ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせて、地球温暖化の原因とされるCO2削減および、省エネルギーを念頭に、既存のガソリンエンジン車の2倍の燃費を実現するとともに、排出ガス中のCO、HC、NOxを規制値の約1/10に低減した車「プリウス」を開発した。同様に、図書館のハイブリッド化も可能なのではないかと考えた。この車の開発のコンセプトには、環境取組プラン「ECO-PROJECT」◆8)がある。ハイブリッドという技術のバックボーンには、社会や消費者を視野に入れたコンセプトが必要であって、優れたコンセプトがあってこそ難しい局面を乗りきることができる。
ハイブリッド図書館を展開すると以下のようになる。
1)高度化
高度化では電子媒体と紙媒体をミックスした資料提供を行う。電子媒体の資料では、受入業務、書架スペース、職員さえも不要になり、経費的な効率は格段に高まるのではないか。しかし、そのためのネットワーク基盤整備の財源の確保ができるくらいなら、紙媒体の資料を維持する旧タイプの図書館を選択することも可能なのではないかとも考える。
2)効率化
効率化では、係の統合や蔵書構築方針の転換によって図書館サービスの再構築を行う。現在の購入タイトルを維持するだけの資料費を支出することが適正なのか。購入タイトルを半分にする代替として、図書館が代金を負担する文献複写に資料提供をシフトするために、雑誌係員を文献複写依頼業務に転換した方が安上がりなのではないか。さらに、学生募集の呼び物として、教養・趣味・娯楽の雑誌を大量に買い込んで、館外貸出を行い、図書館を活性化することのほうが、大学経営にとっては効率的なのではないか。ただ、慣れきった従来のやり方に安住している図書館員が効率化の障害として立ちはだかってくるだろう。
3)共生化
共生化とは関連業界とのマルチソーシング(共同運営)による共生進化のことである。従来、図書館が行っているテクニカルな業務(発注、受入、目録)などの業務を代理店や書店にアウトソーシングすることにより、代理店は新たなビジネスを獲得できる。図書館は浮いた人員で図書館の業務を拡大できる。図書館は、単純な文献提供から一歩踏み込んで、個人的な研究テーマに沿った文献リストの作成や、学生への授業のための教材作成の援助などの、情報の評価・加工にまで機能を拡大し、大学との協力関係を強めるべきである。
4)グローバル化
グローバル化とは、経済と情報のグローバル化に対応した図書館のポジショニングである。既存の枠組みにとらわれないグローバルな観点から、国内外の代理店、出版社、研究者と協力して、図書館業務の学術情報の流通サイクルをもっと円滑にできないのか。また、代理店の価格競争に頼って雑誌の購読価格を引き下げるのではなく、研究者の所属機関である大学として、流通サイクルに応分の費用を積極的に負担すべきではないのか。
大学のグローバル化も活発になっている。(財)大学コンソーシアム京都◆9)では「地域社会、産業界、大学の新たな連携を構築し、大学教育、地域社会、産業界の活性化に寄与する」事業を推進しており、図書館に関連する事業として、大学間の単位互換や図書館の一般公開が行われている。図書館のコンソーシアムの動きもグローバルな大学の動きと連動させるべきである。
1)〜4)にまとめたようなあらゆる手段を動員して、ハイブリッド図書館へと自己改革し図書館の機能拡大・強化に取り組むことが今後の図書館運営における課題となる。
・目録:雑誌を新規に受け入れる場合や、誌名変更が起こった場合には「目録」を作成する。
・受入:雑誌の最新号が毎月、毎週きちんと欠号なく届いているかどうかの納品チェックを行う。
・製本・登録:一年分の雑誌を合冊製本し、大学の資産として登録する。
・ILL:自館で所蔵していない雑誌の論文を図書館間の相互協力で取り寄せる。
・書架管理:新着雑誌や製本雑誌は毎年膨大な分量が書架に蓄積されるため、日常的な書架スペースの再配置と、数年に一度の開架書架から閉架書庫への雑誌の移動を行うなど、限られた書架スペースを有効に活用するための管理を行う。
【表1:雑誌業務の電算化等の状況】
| 業務
状況 |
支払 |
|
|
|
|
管理 |
| 電算化 |
|
|
|
|
|
|
| EDI |
|
|
|
|
|
|
| アウトソーシング |
|
|
|
|
|
|
業務システムが電算化されたことにより、図書館と相手側とのEDIが可能になっているが、雑誌業務の中でEDIが実現しているのは、学術情報センターの総合目録システムによって稼働している「目録」と「ILL」である。
「受入」EDIは、購読代理店が図書館に代わって雑誌の各号の受入を行い、その受入データをフロッピーなどを介して図書館システムに読み込ませる「一括納入方式」として提供されている。「一括納入方式」については次章で詳しく述べる
「発注」EDIについては、「単行本の発注」では、大手の書店からEDIによる発注システムが90年代後半から提供されているが、「雑誌の発注」は日本国内では開発されていない。価格交渉や購読中止など図書館と書店側でのやりとりが頻繁でシステムが複雑になる点、お互いのシステムにおけるデータ形式の標準化の遅れなどが、図書館と購読代理店の間の「雑誌の発注」EDIを遅らせている。すでに代理店と出版社の間のEDIは一般的になっており、図書館業務のアウトソーシングが進展すれば、図書館と代理店の間のEDIは急速に実用化されるだろう。
次は、雑誌業務のアウトソーシングの状況である。「製本」については、雑誌の合冊製本を専門に行う製本業者による完全なアウトソーシングである。「発注」については、「外国雑誌の発注・支払」は、ごく一部の図書館が行っている海外の出版社への直接購読をのぞいて、出版社への発注・支払を、購読代理店が図書館に代わって行うアウトソーシングである。「国内雑誌の発注・支払」は、書店や大学生協へのアウトソーシングが主流であるが、学協会で出版する学術雑誌や抄録集などは、図書館が直接に発注・支払を行っている。「目録」については、公立図書館では目録と装備を完了した図書を購入するアウトソーシングであるが、大学図書館の場合は、学術情報センターの目録システムを使ったコピー目録の部分が一種のアウトソーシングといえる。
1)総合目録
電算化による大きな業務改善は「学術雑誌総合目録」である。総合目録の編纂業務が70年代半ばに電算化されたことにより、その製作期間は大幅に短縮され、総合目録の制作過程で蓄積された書誌・所蔵データは総合目録のオンラインによる提供を可能にした。さらに、オンラインによって提供された総合目録は、図書館業務の電算化を終了した個々の図書館にとって、総合目録事業への自館の所蔵データ提出作業を大きく省力化した。
全国の大学図書館が所蔵している図書や雑誌の所蔵状況を示す総合目録は、自館で所蔵しない資料の文献複写・現物貸借による利用を可能にし、利用者に提供できる資料の範囲を、全世界で出版されるあらゆる資料にまで拡大した。また、総合目録の一つの書誌に全国の図書館の数十・数百の所蔵をぶら下げることにより、図書館の「目録」業務は大きく省力化されることとなった。学術情報センターによる電算化・ネットワーク化された図書・雑誌総合目録システムの稼働は、大学図書館システムの方向--データ形式や図書館業務の枠組みなど--を大きく決定したといえる。
2)個別館の「受入」と「目録」
図書館業務の電算化と学術情報センターの総合目録事業によって、個々の図書館の「受入」と「目録」はその仕組みを大きく変容していった。マニュアル業務の時代には、ビジブル・インデックスによる受入業務と、冊子体目録で提供される所蔵目録は、有機的に結びついていなかった。A雑誌の10巻4号が受け入れられ、10巻3号が欠号であることが判明しても、その所蔵データが雑誌目録に反映するのは冊子体目録が改訂される数年先のことであった。しかし、電算化された現在は、受付された所蔵データは即座にOPACに反映され、さらにインターネットを通じて自宅からでも所蔵データを確認することが可能になっている。また、数年に一度の総合目録への自館所蔵データの提出も、磁気テープに落とし込んだ所蔵データを送るだけで終了してしまう。
受付〜目録〜総合目録までの作業が統合されて処理されるようになって、OPACの所蔵データは最新状態に保たれ、学術情報センターの総合目録で一元的に管理される目録データでは、同じ雑誌についての目録データを個々の館が繰り返し独自に作成する作業から解放された。「目録」と「受入」に関しては、電算化、EDI、アウトソーシングの効果が大きい。
3)配架誌名
雑誌を書架に配架する際の配列要素には、請求記号を用いる館と、誌名を用いる館がある。医学・理工学系の図書館では引用文献や二次資料の検索結果から論文を探す場合が多いので、誌名順配架がほとんどである。一方、戦前から存在する歴史の古い図書館では、図書と同一の配架体系を雑誌の配架にも導入しているため、請求記号による分類順配架が多い。
「書架管理」に関わる電算化の部分では、雑誌を書架に並べるための、誌名または請求記号に若干の問題を残している電算化システムがある。
分類順配架では、雑誌の合冊製本がすんだ段階で図書と同じように製本された雑誌の1冊ごとに請求記号と財産登録のための登録番号がふられ、誌名順に配列されたカード目録に所蔵データが追加されていく。利用者は誌名によってカード目録を検索し、その雑誌の請求記号を調べることになる。電算化システムでもこの物品管理の枠組みがそのまま踏襲されている。雑誌名でOPACを検索し、製本画面を開くことにより必要とする巻号の請求記号を知るという流れである。この物品管理の枠組みを、電算化の際に見直す必要があったと考えるのであるが、当館では分類順配下を採用していないので、これについては深く追求しないでおくこととする。
当館の採用する誌名順配架での問題は、学術情報センターの目録の誌名と当館の従来からの配架誌名が一致しない点と、当館の雑誌システムでは、配架誌名のデータ項目が用意されていなかった点である。この問題を解決する方法は二通りある。1)目録の誌名にあわせて実際の雑誌の配列を並べ替える、2)目録に配架誌名を書き込む。二通りのうち当館では前者を選択して、当館独自のデータ項目である「配架誌名」を追加した。従来は当館の中で一つであった誌名が、「総合目録としての誌名」と「自館での配架誌名」の2つが必要になったわけである。
受付〜目録〜総合目録までの作業が統合処理され標準化されたことによって、各館ごとに異なった処理をしていた雑誌の配架などの「書架管理」の場面で不整合が生じ、ある意味ではシステムが複雑化したといえる。
・代理店による出版社への雑誌の注文と送金の代行
・出版社による雑誌の図書館への送付
紀伊国屋書店では「ACCESS(Air-cargo, Check-in, Consolidation, Economical, Satisfaction, System:アクセス)」、丸善では「MACS2:Maruzen Accelerated Consolidation System:外国雑誌一括納入システム:マックス・ツー」、SWETS社では「ファースト・サービス◆◆正式名称?◆◆」というサービス名で提供されるようになり、大学図書館や専門図書館における人員不足を補う有効な手段として多くの図書館で採用されている。特に、雑誌受入を専門に行う係員をおけない図書館では、館員のパワーを利用者サービスに振り向けるための有効な手段となった。早期の欠号チェックと、クレームによる納入率の向上は認められるし,一括納入方式を使わなければ業務の成り立たない小規模な分室や専門図書館などにとっては有効なサービスである。
一括納入方式は、郵便事情が劣悪で欠号が日常的に発生する国のために欧米の購読代理店で開発されたシステムで、いったん代理店に図書館の購読タイトルをすべて集めて、個々の図書館単位でひとまとめにして送り届けることにより欠号の発生を抑え、欠号補充に関わる経費を軽減しようとするシステムである。このシステムは、80年代から日本に進出してきた欧米の購読代理店が、国内の購読代理店との差別化のために1990年前後から提供を始めた。このシステムの特徴は3つある。
・エアカーゴの導入で少なくなった欠号発生率のさらなる縮小
・現地調達による価格面の優位性
しかし、米国の調査◆10)【図1】では、雑誌の受入(チェックイン)を外部委託している例は139館中1館で、皆無といってよい。これは、一括納入方式には通常の手数料とは別に手数料が加算され、結果的に購読価格がかなり上昇するという米国の事情も大きく影響しているが、「受入」は図書館の業務だとの強い自負が存在している。それ故に、一括納入方式の客観的な評価もしないで、「受入」をアウトソーシングすることには、個人的には強い不安を覚える。その反面、一括納入方式で雑誌を購入しながら、当館では届いた雑誌に対して相変わらず「受入」を行っているのであるが、その重複作業には強い疑問を感じるのである。改めて共生進化の視点から一括納入方式を見直してみる必要があろう。
【図1:アウトソーシング調査(米国 1996年)】
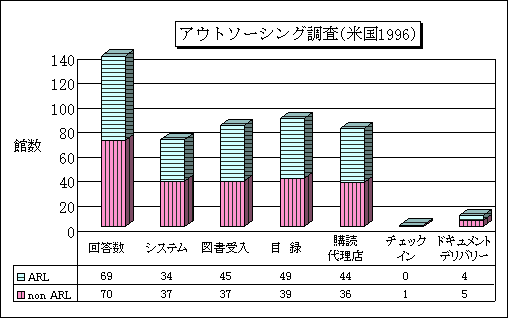
図書館の機能は、利用者の要求に応えて物資や情報を調達し前線へ補給することであるが、外国資料の調達に関しては「出版社、購読代理店、図書館」という流通ルートが確立しており、完全なアウトソーシングである。購入する雑誌の選定と、代理店の選択、購入価格の交渉が図書館の仕事となる。であるから、図書館の資料調達能力は、その図書館が使っている購読代理店の調達能力の如何にかかってくる。
調達能力では、SWETS社、EBSCO社、今は解散してしまったFAXON社などの外資系の購読代理店と国内代理店との差は歴然としている。出版社と地理的に近く、言語を同じくし、顔の見えるところで取引をしているせいもある。ALA大会で、図書館員や出版社、代理店が一堂に会するという機会をつくり、雑誌の流通システムを改善しようという意識も違う。例えば、SISACのバーコードシンボルの印刷やDOIの開発、その規格化などがある。雑誌研究会も3者で行う。共生化の一つの形態といえる。このような共生関係が日本には育たない。serialst-jがその手伝いをしたい。
同じ一括納入方式という仕組みを使っても、その調達能力が異なっているため、国内代理店が逆立ちしても外資系に勝てる道理はない。欧米の代理店の合理的な考え方と雑誌や情報の調達能力の差は、一括納入方式を導入したからといって簡単に埋まるものではない。
受入(チェックイン)業務は雑誌業務における中核業務であり、できればアウトソーシングすべきではないと、個人的には考えている。個人的には、一括納入方式は「図書館愚民化政策」と考える。
一括納入方式が日本に定着した理由にはもう一つ考えられる。海外代理店による一括納入方式での価格が、国内代理店の直送方式での価格より低価格に抑えられた点である。つまり、海外代理店が海外で設定していた直送方式での価格に、一括納入方式の手数料を加算してサービスの上乗せをしても、国内代理店との価格競争に勝てたからである。低価格が実現できるのは、取扱点数が多く仕入れ原価が安いことと、雑誌の購読代理店に特化してシステム効率の良いことにある。
より業務効率のよいシステムをもったアウトソーシングの会社が新規参入することで、既存の会社のシステムも引き上げられたといえる。民間企業ではこのような競争原理が働くため、業務改善が進行し、よりよいサービスが従来価格で受けられるようになる。この辺は、非営利機関である大学も大いに学ぶ必要があるだろう。
しかし、振り返ってみると、業界標準となった一括納入方式を有効に活用できていない図書館も多く存在している。
1)代理店より提供される受入データの入ったフロッピーを自館のシステムに流し込むモジュールがない
2)受入点数が少ないためチェックインを省略しても節約できる時間がわずかで何となく雲散霧消してしまう
3)代理店のつくる受入データを信頼することができない
4)代理店より付加価値の高い受入を行う
当館もそうであるが、一括納入方式で納品された雑誌を、さらに自館でも受入を行っている図書館は、「受入業務の省力化」の部分では、一括納入方式に支払った手数料の大半を無駄にしていることになる。そこで昔ながらの直送方式に改めようとしても、大手の代理店ではそのようなオプションはすでに提供されないのである。何ともおかしなアウトソーシングである。
図書館業務の現場からみた電子雑誌の特徴は以下のようになる。
・ネットワーク環境の整備状況でサービス効率が決まる。
・購入のための予算科目が従来の枠に収まらない。
・全く新しい業務の追加となる。
・電算改善の問題として共通様式の作成:全国的な請求書類、欠号連絡票の統一など
・出版社との関係強化と代理店との協力関係の構築
・ハイブリッド化による「道具としての図書館」の効率性の追求
・積極的な戦略としてのアウトソーシングへの移行
とはいえ日常の業務はかなりハードで、きれい事ではすまされない。1995年は二次資料を6点400万円、1996年は一次資料を30点700万円、1997年は60点700万円、1998年は70点1,000万円。これが、当館で購読中止した外国雑誌のおおよその点数と金額である。購読価格の値上がりは毎年10〜20%に達し、雑誌の予算はほとんど伸びない状況がここ数年続いている。中止する外国雑誌のタイトルを決める作業は、タイトルの選定から始まって、教員との調整、代理店との価格交渉とハードな作業が続く。大変な作業であり、あまりにも業務改善とはかけ離れた仕事であり、いろいろと悩み、考えた結果が先に述べたハイブリッド図書館であり、それを展開した高度化、効率化、共生化、グローバル化である。
さらに、文献提供という観点から見た場合、雑誌係の担当となる「雑誌を図書館で所蔵する」行為と、参考係などの担当となる「文献複写で取り寄せる」行為が機能的には同等であり、機能分担の再構築まで踏み込んだ図書館全体の組織改革も必要である。
『情報を使う力』◆11)では、大学の使命を「情報リテラシーを身につけた市民の育成」として、大学の資源である図書館および図書館員の有効活用を提言している。
・研究の生産性向上への図書館および図書館員の活用
・地域サービスの改善
・大学の経営管理活動への支援
1) 学術審議会学術情報資料分科会学術情報部会. 大学図書館機能の強化・高度化の推進について(報告)(平成5年12月16日). [online]. [引用:1999-03-30]. 入手先:<http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/anul/material/houkoku.html> 「(1)学習図書館機能の強化 学術情報(図書資料、マイクロ資料、電子化情報等)への容易なアクセス、学習・研究スペースの確保、新しい電子媒体資料等を有効に活用するための施設・設備の整備、開館時間の延長や土曜・休日開館、要員確保。 (2)留学生や社会人学生のためのサービスの充実 (3)大学図書館の地域社会・市民への公開」[6.学習活動の場としての図書館機能の強化 より]として、図書館の新たな方向が示されている。
3) 大学審議会. 21世紀の大学像と今後の改革方策について―競争的環境の中で個性が輝く大学― (答申)(平成10年10月26日). [online]. [引用:1999-03-20]. 入手先:<http://www.monbu.go.jp/singi/daigaku/00000303/> この答申により図書館の設置母体である大学が改革を指向すれば、図書館もそれに従わなければならない。
4) 高鳥正夫; 館昭編. 短大ファーストステージ論. 東京 : 東信堂 ; 1998.4. 例えば、大学が学生の生涯における学習の第一段階として位置づけられるという新しい方針を大学が策定すれば、必然的に図書館も変わらなければならない。
5) 山本宣親著. 図書館づくり奮戦記:本と人・人と人が出会う場所をめざして. 東京 : 日外アソシエーツ ; 1996.10.
6) 竹内紀吉. 地方自治体における図書館経営の経済効果(情報の経済<特集>). 情報の科学と技術 1994.5 ; 44(5) : 270-273.
7) 特集:図書館経営論の課題. 現代の図書館 1998.12 ; 36(4) : 223-285.
8) トヨタECO-PROJECTのページ. [online]. [引用:1999-03-20]. 入手先:<http://www.toyota.co.jp/eco/index.html>
9) (財)大学コンソーシアム京都<http://manzoku.topica.ne.jp/daicen/index.htm>
10) Claire-Lise Benaud, Sever Bordeianu. Outsourcing library operations in academic libraries : an overview of issues and outcomes. Libraries Unlimited ; 1998.
10-1) PubMed利用法<http://www.kdcnet.ac.jp/hepatology/howto/pubmed/pubmed.htm> PubMed 徹底活用講座<http://www.asahi-net.or.jp/medical/search/pubmed0.html>
11) パトリシア・セン・ブレイビク, E. ゴードン・ギー (三浦逸雄, 宮部頼子, 斎藤泰則訳). 情報を使う力:大学と図書館の改革. 東京 : 勁草書房 ; 1995.1. (Information literacy : revolution in the library. c1989の翻訳) 図書館の機能拡大と大学指導者へのアピールについての指摘を参考にして図書館の業務改革に取り組みたいものである。
【図書館の機能拡大】
・授業改善への、図書館および図書館員の活用
・研究の生産性向上への、図書館および図書館員の活用
・地域サービスの改善
・大学の経営管理活動への支援:大学の経営計画策定において、図書館および図書館員は図書館の情報資源を使って、新聞の切り抜き、雑誌記事、単行本、各種の報告書、オンライン・データベース、さらにインターネットによる競合他社の情報など、戦略情報の収集・分析・評価を行うことができる。図書館員は情報管理の専門家集団として、もっとも効率的に、且つ、網羅的に戦略情報を提供できる。さらに、管理者の情報リテラシー(情報を使う力)を高める支援を行うこともできる。図書館および図書館員の有効活用は大学の生産性を高める業務改善につながる。
【大学指導者に対し、図書館についての注意を喚起すべき点】
・図書館資料価格のインフレ傾向は消費者物価指数を大きく超える。
・新しい情報技術は図書関係費をさらに膨張させる。
・図書館協力事業の利点と限界:サービスは向上するが、経費を抑えることはできない。
12) 大学図書館員の育成・確保に関する調査研究班. 大学図書館員の育成・確保に関する調査研究班最終報告(平成8年7月) [online]. [引用:1999-03-20]. 入手先:<http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/anul/Kdtk/Rep/55/55.html>