大学図書館の雑誌担当者にとっての外国雑誌購入に関わる諸問題は、未着欠号、総代理店制度による円建て価格、地域による差別価格、購入価格の上昇による価格問題のクローズアップ、円高差益の還元、外資系代理店の参入、国内代理店の新方式、代理店間の価格競争の激化などである◆1)◆。「Serials Crisis: 学術雑誌の危機」といわれて久しいが、外国雑誌の諸問題を「価格」だけで捉えようとする狭い視点は、図書館サービスの本質である「文献提供」を広範囲に見渡そうとする議論に統合されつつある。学術情報流通サイクルのなかで図書館が右から渡された情報をそのまま左に送るだけの単純なサイクルは、世紀末の残りの数年間で終わってしまうだろう。何故このサイクルに参加しているのか、このままのルールでサイクルを続けていくのか、別のゲームを始めるのか、このサイクルに組み込まれている代理店、出版社、研究者とともに考えるときがやってきている。
ここでは、最初に大学図書館における雑誌購読業務の流れを示し、大学図書館にとってのマイナス要因(価格問題の周辺)とプラス要因(円高と代理店の努力)を整理して、最後に今後の大学図書館の文献提供サービスのキーワードを考えてみたい。
外国雑誌の予約購読を代行する業者を、取次、取次店、取次代理店、エージェントなどと呼び、書店が代理店業務をおこなうので書店とも呼ぶこともあるが、すべて代理店とした。国内や外資系に限定する場合は、国内代理店、外資系代理店とした。
1 予約購読の手順
大学図書館の外国雑誌の購読は、代理店と図書館の間で購入契約がかわされ、出版社への雑誌の注文と送金を代理店が代行して行い、出版社によって雑誌が毎号確実に図書館に送り届けられる。代理店を利用しない直接購読の例も少数は存在するが、大学図書館の外国資料の購入はすべて代理店経由といってよい。外国雑誌の購入にあたっては、出版社側による予約購読の原則がある。
・1年単位の予約制であること。
・年間購読料の前払制であること。
・予約期間中の値上がりに精算請求があること。
・出版社から予約者への直送制であること。
(後述するチェックイン方式が主流に
なりつつある)
この原則に従って雑誌購読の手続きが毎年繰り返される。この手続きは4つのパターンの組み合わせで処理内容と実施時期が異なる。図書館の設置母体が国公立大学か私立大学か、契約する代理店が国内代理店か外資系代理店か、雑誌の納入方式が直送方式かチェックイン方式か、契約の方式が随意契約か競争入札か、などである。個別の事情により手順は異なるが、大学図書館における外国雑誌購読の流れはおよそ次のようになる。
【外国雑誌購読の年間日程】
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6−10月 (海代)契約開始:
以後の手順は国内代理店に準ずる*1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7月 ( 図 )翌年タイトルの追加、削除
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
8−9月 (国図)競争入札:
以後の手順は随意契約に準ずる *2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9月 ( 図 )翌年タイトル決定:
購入タイトルを代理店に通知
( 代 )定価見積
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
10月末 ( 図 )代理店との通貨毎の価格交渉
(3つの価格算定方式) *3
( 代 )出版社への発注、送金 *4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
12月初旬 ( 図 )価格決定
( 代 )価格見積書
(私図)契約、代理店へ支払
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3月上旬 ( 図 )精算
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4月− (国図)契約、代理店へ支払 *4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
( 代 )国内代理店 (海代)外資系代理店
( 図 )大学図書館 (国図)国立大学図書館
(私図)私立大学図書館
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*1:早期契約:外資系代理店では、秋の契約・支払を春におこなうことで3%程度の割引がある。
*2:競争入札:国の契約制度には一般競争契約、指名競争契約、随意契約の三種類の方法があり、図書館の資料購入にあたって、従来は随意契約がとられていた。しかし、昨今の競争原理の導入により競争入札も実施されるようになり、代理店間の価格競争が激化している。
*3:価格算定方式:価格の算定方式には、係数方式、CPレス方式、個別タイトル方式の3つがある。係数方式は、外国資料の外貨とその通貨の実勢レートに手数料を加算した係数とを掛け合わせて購入価格とする。CPレス方式は、代理店のカタログの円定価に一定の値引き率を掛け合わせて購入価格とする。個別タイトル方式は、個々のタイトルの特性(価格帯、出版社、出版国、通貨、刊行回数、取引条件)を考慮してタイトル毎に手数料を算定する方法である。
*4:支払時期:私立大学では前年末までに代理店に支払う、国立大学では予約購読の当該年度に支払う。◆2)◆
2 価格問題の周辺:マイナス要因
『大学図書館と学術コミュニケーション』◆3)◆では、蔵書、経費、出版の現状分析を行い、学術情報流通における問題解決の切り札として、電子的な新技術の将来性に期待をかけている。
【『大学図書館と学術コミュニケーション』の要約】
研究のパート1: 学術図書館の現状
1. 大学予算に占める図書館予算の割合を増大させることができず、比率が縮んだ。
2. 資料費と製本費:資料購入経費は、総図書館経費に一定の割合であり続けたが、単行本と逐次刊行物の間で経費の再配分があった。
3. 単行書:1970年代と1980年代に、大学・研究図書館の受入冊数の増加は事実上停止したが、一方で、国内および国際的な出版点数は、年々増加し続けた。
4. 逐次刊行物:多くの人々の間で、図書館の今日的難題の中心として「学術雑誌の危機」について話されたが、その危機は価格問題であり、特に自然科学雑誌の価格問題であった。
5. 過去20年間にわたって、人件費の割合は減少を続けたが、一方で「他の運営費」(コンピュータ化による)の増加が顕著であった。
研究のパート2: エレクトロニクスの将来性
6. 前半部分で述べられた困難な状況には、様々な取り組みが必要であるが、電子テキストの供給、管理、利用面での役割の増加は、最もドラマチックな可能性を秘めている。
7. つい最近まで、図書館の自動化は既存の内部の機能(貸出、目録、受入)に向かっていたが、自動化の範囲はずっと広くなっている。
8. 現時点では、電子出版は多くの種類の媒体・手段でなされている。
9. 学術出版は、学究的な名声と強く結びついている。保守勢力に新しい仕組みを認めさせることが必要である。
10. 電子テキストの供給のための選択がおびただしく多い。現時点でのそれらのコストは不安定である。
11. キャンパスのコンピュータ・コミュニケーション基盤は、新しい技術を可能にするためにグレードアップされる必要がある。
12. 出版過程の伝統的な役割は変化を受けるだろう。
日本の大学図書館を米国と比較してみると、国立大学図書館では米国と同じ症状が現れているが、私立大学図書館ではそうでもない。価格問題が深刻なのは、洋雑誌への配分が大きく、なおかつ情報化の進行している国立大学図書館や規模の大きい私立大学の図書館である。
【表1:図書館の経費配分 1983年と1993年】 詳細データ
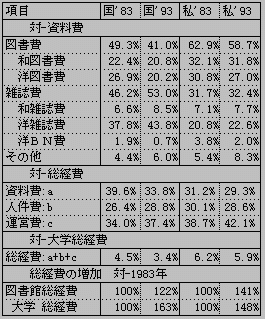
【文部省大学図書館実態調査報告より作成】
米国と同様に大学総経費に占める図書館経費の割合の減少が国立大学では著しい。
資料費の図書館経費に占める割合は国立も私立も減少しているが、国立での減少が大きい。米国では人件費から運営費へ再配分があったとされるが、日本では資料費から運営費への再配分がなされている。雑誌費と図書費の間での経費配分は雑誌費にウェイトが移っている。この傾向は米国と同様である。洋雑誌費への資料費配分比率の増加は国立でより顕著である。外国雑誌の価格問題はより国立に強い作用を及ぼしている。
国立は、図書館業務の機械化の後、学内LAN、インターネット、マルチメディア等の情報基盤を整備し、電子図書館などの将来システムへの対応をすすめている。私立は図書館業務の機械化までは到達していても情報基盤の整備は国立ほど進んでいない。そのせいか運営費への図書館予算の配分比率の増加が少ない。私立の運営費への配分比率(比率の増加ではない)が大きいのは、国立より図書館総経費の額が小さいため固定的にかかる運営費への配分が大きくなっているせいである。
今後は、大学内での経費配分と図書館内での経費再配分についても調査・研究がなされるべきである。
3 円高と代理店の努力
3−1 20年間にわたる円高傾向
1982年を基準に、1995年までの各国通貨の換算レート(代理店との価格交渉の基準日での)を示す。ドルとポンドにたいする円の強さは10年間で2倍である。マルク、ギルダーにたいしても3割ほど円高になっている。
【図1:各国通貨換算レート1982年比】
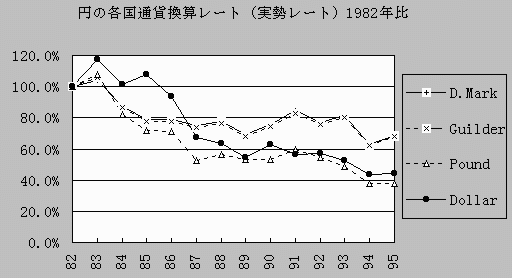
雑誌の購入価格への換算レートの影響は非常に大きい。論文生産量の増加を反映した年間総ページ数の増加よりも、購読数の減少つまり図書館のキャンセルが大きな価格上昇の要因となっている。McCarthyは米国大学図書館の大幅なキャンセルを Serial Killers と表現している。◆4)◆
【表2:米国の1997年雑誌価格上昇予測】◆5)◆
北 米 欧州大陸 英 国 その他
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
物価上昇 2.8% 2.5% 2.1% 2.0%
出版経費上昇
紙代 0 0 0 0
郵送費 0 0 0 0
ページ増加 3.0% 3.5% 3.5% 2.0%
キャンセル 4.5% 5.0% 4.5% 3.0%
通貨上昇 0 0 0 0
to -3% to -3%
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
総 計 10.3% 8.0 7.1 7.0%
to 11.0% to 10.1%
3−2 代理店の努力
この後の「3-3 代理店の機能」でふれるチェックイン・サービスの価格算定には個別タイトル方式が適応されることになった。100ドルのA雑誌と2,000ドルのB雑誌の2タイトルを購入している図書館では、1ドル 100円、係数15%の係数方式から、個別タイトル方式へ移行すると11,500円の節約になり、代理店は同額の減収になる。
【表3:係数方式と個別タイトル方式の差額】
手数料 係 数 購入価格
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
個別タイトル方式
A雑誌 5,000 (50.0%) 15,000
B雑誌 15,000 ( 5.0%) 215,000
計 20,000 ( 9.5%) 230,000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
係数方式
A雑誌 1,500 15.0% 11,500
B雑誌 30,000 15.0% 230,000
計 31,500 15.0% 241,500
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
差額 11,500 11,500
現実はこんなに単純ではないが、高額誌の購入価格が下がることで、予算不足が深刻だった図書館は一息つけることになった。よりリーズナブルな算定方式にしたという国内代理店の説明より、外資系代理店との価格競争対策と捉えるほうが図書館員には納得がいくのである。そうすると、従来までの算定方式が代理店にとって有利すぎたとの考えも成り立つのであるが、価格体系と納入方式における国内代理店と外資系代理店との間の格差がなくなったことで良しとしたい。営利企業体の体質改善と経費削減の努力は大学図書館も見習うべきである。
慢性的な価格上昇と、図書館のこれも慢性的な予算不足の間で、雑誌購読の代理店はいかに利益を確保するかに懸命である。 Alster◆6)◆は、代理店を an interesting niche (niche:活動範囲、適所)と表現している。「出版社からの仕入れの際の数%の割引と、図書館の購入を取り次ぐ際の3〜4%の手数料」が営業収益となり、薄利にも関わらず多売でない特異な商売ということだろうか。
日本の大手の代理店は、店舗で単行書も販売し、出版事業も行い、図書館関連用品や備品までも手広く商っている。総体で利益はあがっていても洋雑誌部門が芳しくないという代理店側の説明が信憑性を帯びてくる。
日本の大学図書館では、十分といえないまでも安定した図書館経費の増加を背景に、円高と代理店の手数料カット(手数料率の縮小は、ほとんどが国立大学図書館の努力である)が、雑誌の値上りをかなり相殺していた。円高という神風やこれら好条件の方向が変わったときには、何が大学図書館を待ちかまえているのだろうか。
3−3 代理店の機能
代理店が図書館業務を代行している部分は多い。出版社の予約と支払にかかわる全業務(洋資料をすべて直接購読するなど今の大学図書館では不可能である)、出版社への支払時期と大学からの支払時期のズレを埋めること、欠号請求(ダイレクトクレームは出版社の動きを実感できる数少ない機会であった)などである。これらはすべて代理店という業態が定着しているなかでことさらに強調することではないが、外部委託という形式での外部資源の活用が日常化している現在、あらためて図書館業務と代理店業務との関連を考えてみることも無駄ではない。
90年代になって国内代理店も外資系代理店にならって、出版社から図書館に直送する方法を改めて、いったん代理店の集荷基地に雑誌を集めて、そこで受付チェックを行い出版社に対する欠号請求を済ませてから、個々の図書館への雑誌をまとめて宅配するチェックイン・サービスを開始した。いわゆるチェックイン方式である。◆7),8),9)◆
このチェックイン・サービスでは、図書館は受付チェックのデータをフロッピーなどの電子媒体で図書館システムに取り込むことにより、自館での受付業務を簡略(もしくは省略)でき、欠号の発生が減少し、欠号の補充も改善される。チェックイン方式は外資系代理店により提供されていたサービスであり、図書館業務の資料組織などのテクニカルな部分を外部委託し、不足しがちなマンパワーをより生産性の高いサービス部門や企画部門に振り向けようとする図書館運営の一連の動きにあわせて生み出されたサービスである。このような外部資源の活用にあたっては、マンパワーの再配分をおこなうことが重要であり、再配分のない外部資源の活用などありえない。
3−4 出版者との関係
外国雑誌の購読において、代理店は契約を代行するだけで契約の主体は図書館と出版社であり、図書館からの欠号請求は「慣例として」代理店が出版社に取りついでいるというのが代理店の主張であった。過去において、この代理店の主張の解釈をめぐって欠号補充の責任の所在が問われてきたが、代理店のチェックイン・サービスによりこの問題は解決した。代理店の集荷基地に雑誌を集荷することで図書館と出版社の間の契約関係が消滅し、自動的に代理店が雑誌の完全供給に責任を持つことになったのである。
従来から日本においては図書館と海外学術出版社の関連が希薄であった。それは、代理店の洗練された業務システムが「わがままな」図書館の要求をかなえ続けたからである。それ故に出版社の値上げにたいして価格問題の矛先が向かうことはなく、図書館の要求が代理店の利益の縮小という方向に安易に走りすぎていた。また、国内代理店がおかしな方向に自信の存在意義を強調してきたことも問題であった。図書館員はチームで仕事をすることが苦手なせいか(国立より私立でその傾向が強いようにみえる)、情報流通におけるパートナーシップにも無頓着でありすぎた。この点は謙虚に反省すべきである。
おわりに--世紀末のキーワード
図書館と代理店の関係の再構築はもちろん必要であるが、これからの図書館は文献提供(情報提供)サービスの運営にあたって、どのような戦略を採用すればよいのだろうか。キーワードは、アウトソーシング、図書館第二出版市場論、情報リテラシーである。外国雑誌購入にかかわる業務レベルの諸問題は、これらのキーワードに対応していくなかから必然的に解決していくだろう。
バッシュ◆10)◆のいっているアウトソーシング(out-sourcing:外部資源の活用)は、バーチャル・コーポレーション(VC:virtual corporation:社内外と協力し、自社が持つよりも多くの資源を集結できる企業のこと)の前兆とされている。外国雑誌の場面では、チェックイン・サービスが格好の事例である。契約データの電子的な交換や◆11)◆、未刊行号に対する欠号クレーム(early claiming)を抑制するための刊行状況データ照会システム◆12), 13)◆の開発により、図書館業務のアウトソーシングの機会がさらに増大することに注目したい。
窪田は「図書館第二出版市場論」◆14), 15)◆で「図書館は、在来の自己規定を修正し、第二市場における出版事業に参加することを自覚すべき時に来ている」として「自覚しようとしまいと、図書館はすでに、蓄積された情報の再利用という事業に組み込まれており、これを受け身で捉えるか前向きに積極的な利用者サービスとして取り組むかの岐路にある」との考えを示している。UnCover◆16)◆のような仕組みがこれにあたるのであろうか。また、この種のサービスを、学術雑誌を出版している商業出版社や学協会はどのように捉えているのであろうか。今まで野放しになっていたILLからの著作権料の自動徴収システムとして歓迎することもできる。しかし、大学図書館の雑誌のキャンセルの代替手段◆17)◆にされるのでは手放しで喜べない現象かもしれない
情報リテラシーは、アウトソーシングと第二市場の両局面でも求められており、コンピュータとネットワークを文房具のように利用することは図書館員の必須要件である。米国大学図書館のWWWサイトでは、雑誌のキャンセル・プロジェクトがよく公表されている。テネシー大学(The University of Tennessee at Chattanooga Library)では、雑誌コレクションの見直しのため、1995年9月29日付で研究室の責任者に見直し計画のお知らせ(Serials Review/Cancellation Project)がなされている。「15万ドルの削減のため、各研究室に雑誌のランク付けに協力してほしい。必要度に応じた10段階(カテゴリー10は最高に必要、カテゴリー1はまったく必要でない)の10枚のシートに、雑誌を同じタイトル数だけ記入する。もし各研究室に関連する雑誌が20タイトルあるとするならば、カテゴリー1に2点、以下同様にカテゴリー10まで2点ずつ記入する。図書館で作ったリスト案はWWWサーバーかGopherサーバーの"UTC Library Serials Review."にある。研究室によるランク付けと、利用頻度、価格、その分野における重要性などを考慮してキャンセルリスト案をつくる。その案をさらに研究室に回覧し、いくつかの雑誌をすくい上げて最終リストを作成するので10月16日までに回答をお願いする。」◆18)◆最終リストは、276タイトル、122,229ドル分のキャンセルリストとなって公表されている。◆19)◆
インターネットや電子メールが図書館運営の道具としてスマートに使いこなされている。情報基盤整備の進んだ国立大学図書館も遠からずこのようになって行くのだろうか。そしてその頃、情報基盤整備の立ち遅れた中小の私立大学はどのような図書館運営を行っているのだろうか。インターネットによる情報発信や電子的な文献提供システムの普及が思ったほど図書館で進まないのは、環境の変化による驚きが消化されないまま、図書館員のなかでストレスに変わってしまったせいかもしれない。図書館員の情報リテラシーの欠如を嘆くより、どうすればストレスを解消でき、どうすれば適応できるのかを考えることが急務であろう。
参考文献
1) 長谷川豊祐. 外国雑誌の価格問題--文献紹介と20年間の動向--. 逐次刊行物研究分科会報告. No.51, p.6-31 (1993.12)
2) 森茜; 大場高志. 外国図書の海外直接購入について--国立大学図書館における一方法--. 大学図書館研究. No.37, p.44-52 (1991.3)
国立大学図書館の資料購入は、国の会計規則に従って行われる。私立大学から眺めると何とも複雑な手順で、その手順を省略すれば人員削減になるように思われる。しかし、国立大学図書館が価格引き下げに果たした功績は大きく、それはこの規則ゆえに達成できたことである。
・業者はあらかじめ大学から取引業者の認定を受ける必要がある。
・物品購入にあたっては料金後払いが原則である。
・国の契約制度には一般競争契約、指名競争契約、随意契約の三種類の方法があり、図書館の資料購入にあたっては随意契約が取られていた。しかし、昨今の競争原理の導入により競争入札も行われるようになり、代理店間の価格競争が激化している。
・契約に先立って購入する資料の予定価格の算定を行い、業者による見積金額の点検をおこなう。
3) Cummings, A.M. et al. University libraries and scholarly communication : A study prepared for The Andrew W. Mellon Foundation. The Association of Research Libraries, 1992.11, 205p.
<URL:http://www.lib.virginia.edu/mellon/ mellon.html>にもおかれている。
4) McCarthy, Paul. Serial Killers: Academic libraries respond to soaring costs. Library journal. Vol.119, no.11, p.41-44 (1994.6.15)
5) Harrison, Teri <harrison@faxon.com>. Faxon's 1997 preliminary subscription price projections. Newsletter on serials pricing issues. No.153(1995.1.27)
6) Alster, Norm. Autopsy. Forbes. May 8, 1995, p.77-78 (1995.5.8)
7) 河村正威. 外国逐次刊行物の受入方式の変更について. 国立国会図書館月報. No.373, p.18-19 (1992.4)
8) 母良田功. 外国雑誌購入契約をめぐる諸問題. 病院図書館. Vol.13, no.3, p.77-78 (1993)
9) 長谷川豊祐. 外国雑誌の価格問題--国内代理店新方式の概要とその得失. 図書館雑誌. Vol.87, no.9, p.669-672 (1993.9)
10) バッシュ,N.バーナード. 図書館における定期刊行物の効果的な発注管理:アメリカの現場から.情報管理. Vol.38, no.11, p.967-980 (1996.02)
11) RowCom <URL:http://www.rowe.com>
図書館のインターネット接続されたパソコンで、RowCom社と外国雑誌の発注・契約・支払をするためのプログラム(取扱タイトルのデータを持っており、図書館側で適宜インターネット経由で更新する)を動かして、ペーパーレスで瞬時に支払いも済ませてしまう。人間がほとんど介在しないので、最低の手数料で購読できるというのも一つのセールスポイントである。米国の図書館大会で、デモも行われ話題になっている。日本でも使えるのだろうが、代金の電子決済だけは無理であろう。
12) Pabbruwe, Herman. Kluwer、紀伊國屋書店とICEDIS. アクセスnews. Vol.3, no.1, p.3-4 (1995.1)
13) Bridge, Frank R. Connecting library automated systems to the business world. Library journal. 1994.3.1, p.38-40
Z39.50よりEDIの重要性を訴えている。図書館と書店両者の業務の省力化は、発注データや書誌情報の再入力をなくせるEDIにより実現され、社内努力のみでは不可能なレベルの省力化が可能になる。
14) 窪田輝蔵. 4-2 学術情報:先進諸国における出版と流通−−米英を中心として. 図書館研究シリーズ. No.30, p.419-459 (1993.3)
15) 窪田輝蔵. 科学技術の生産・流通と図書館. 科学技術文献サービス. No.102, p.16-24 (1993)
16) 小田島亙. UnCover(特集エレクトロニック・ドキュメント・デリバリー). 情報の科学と技術. Vol.44, no.7, p.362-367 (1994.7)
約17,000タイトルの学術雑誌の目次データベースサービス(無料)と文献をファックスで24時間以内に配送する電子的な文献提供サービス。固定的にかかる年会費と文献の料金(文献料金、著作権料、ファックス料金の合計で約20ドル)が課されるだけである。17,000タイトル(科学・工学・医学系5割、社会科学系4割、人文系1割)という収録対象誌の多さが魅力である。
17) Hayes, John R. The Internet's first victim?. Forbes. Vol.156, no.14, p.200-201 (1995.12.18)
『インターネットの最初の勝利か? リード・エルゼビア:電子出版の伝統的出版事業への侵略』ルイジアナ州立大学図書館はエルゼビアの出版する 1,569タイトル、446,000ドルの雑誌をキャンセルして UnCover による文献提供に切り替えた。
18) Review/Cancellation Project. <URL:gopher://lupton.lib.utc.edu:70/0F-1%3A9090%3A1Instructions>
19) The UTC library's 1995 serial cancellations final list. <URL:gopher://lupton.lib.utc.edu:70/1D-1%3A9090%3Aserials%20Cancellation%20Project>
大学図書館における外国雑誌の購入について
抄録:
日本の大学図書館では、安定した図書館経費の増加、円高、代理店の営業努力で学術雑誌の価格上昇に対処してきた。これらの好条件の継続は期待できない。大学図書館は今後の文献提供を効率的におこなうために、アウトソーシング、図書館第二出版市場論、情報リテラシーへの取り組みを深めるべきである。
Current issues about foreign serials subscription in university and college libraries.
Abstract:
University and college libraries in Japan have managed to cope under the strain of the increasing costs of serials publications thanks to the steady yearly increase of library budgets, the Yen's appreciation and the efforts of subscriptions agents. However, these favorable conditions are not expected to continue. In order to efficiently offer information services to its patrons in the future, university and college libraries must consider various alternatives such as out-sourcing, the secondary publishing market and information literacy.
長谷川豊祐(Toyohiro Hasegawa)
鶴見大学図書館(Tsurumi University Library)
〒230 横浜市鶴見区鶴見2−1−3
TEL 045-581-1001 内 271
FAX 045-584-8197 e-mail: c05119@sinet.ad.jp