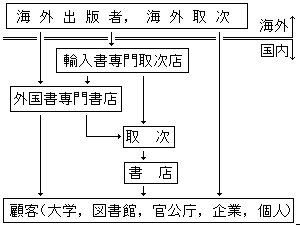
このページは日本図書館協会が発行する『図書館と出版流通(図書館員選書 33巻)』に掲載される私の論文をもとに構成してあります。 長谷川豊祐 HASEGAWA, toyohiro c05119@simail.ne.jp
| 2 外国資料の購入 | 3 外国資料に関わる問題 | |
| 1 洋書輸入業者と国内市場 | 2.1 外国図書の購入 | 3.1 外国雑誌の20年 |
| 1.1 流通経路 | 2.2 外国雑誌の購入 | 3.2 学術雑誌の価格問題 |
| 1.2 国内市場 | 2.3 購入のためのトゥール | 3.3 出版流通の今後 |
明治以来,西欧先進諸国の科学,技術,文化の導入により実現された日本の近代化は,書籍輸入業者の輸入した洋書に大きく依存していた。現在も,そして将来にわたっても,日本の研究開発事業の成立のために外国資料は欠かせない研究資料であり続けるだろう。
外国資料の流通経路(1)-(3)は3つある.最も大きい流通経路は,国内の外国資料輸入業者によって,海外の出版者や取次業者から国内に輸入されるルートである。輸入業者には,卸売を専門に行う「輸入書専門取次店」と,卸売と小売の両方を行う「外国書専門書店」の2種類がある。外国資料輸入業者は、国内では約300店が営業を行っており,そのうち約100店が加盟する洋書輸入協会が業界団体として組織されている。
図書館が資料を購入する「外国書専門書店」の最大手は,外国資料の年商が100億円を大きく超える丸善と紀伊國屋書店であり,この2社は、図書館用品の販売、図書館システムの開発・販売,オンラインデータベースの提供,本の小売、出版、図書館新設のサポートまでをこなす総合図書館情報企業といえる。この2社に続いて年商20億円程度の中堅書店がいくつかある。大手、中堅以外は特定の主題分野や地域・言語を扱う小規模な専門書店である。図書館で購入される外国資料のほとんどすべてが「外国書専門書店」を経由している。
外国書専門書店が果たす「書籍輸入」という特殊な機能(4)により,図書館などの国内の顧客は,外国との商習慣や言語の違いを気にせずに外国資料を国内資料と同じように容易に入手できる。外国資料輸入業者の機能は5つにまとめることができる。
2つ目のルートとして,低価格で発行部数の多い教養・趣味的なペーパーバックや一般雑誌は,国内資料を扱う一般の「書店」からも購入できる。
3つ目のルートとして海外からの「直接購入」も行われている。
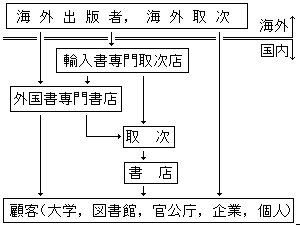
【図:外国資料の3つの流通経路】(5)
国内の外国資料市場の規模は1,000億円(6)と見積もられており,96年の国内出版物販売総額2兆6,980億円(7)の4%にも満たない「小さな市場」である。大学図書館,各種研究所,研究者(文部省の科研費,大学の研究費)が最大顧客であり,市場は文教予算に大きく依存している。
外国資料の輸入額(8)の約85%は欧州と北米の国で占められている。外国資料が「洋書」と呼ばれるのも無理はない。
外国資料の輸入額のピークは90年で,これ以降は減少傾向にあり,外国図書の落ち込みが大きい。減少の要因には,円安による購買力の低下,大学図書館の図書予算の停滞・減少,研究所や企業の資料費の減少があげられる。
外国資料の購入費が統計として公表されているのは大学図書館だけであり,その資料購入動向を10年間にわたって眺めてみる。洋書と洋雑誌を合計した外国資料費の総額は,85年301億円,90年353億円,95年358億円と,90年以降は横這いである。外国資料市場の約4割を占める大学図書館の資料購入動向は市場に大きな影響力を持っており,90年をピークとした外国資料の輸入額の減少傾向は,この辺にも原因があるといえる。
また,資料費に占める外国資料費の割合は,85年57%,90年56%,95年51%で,大学図書館業務における外国資料の占める割合は総資料費の半分を超えているが、減少傾向にある。総資料費に占める洋雑誌の割合は変わらないものの,洋書の割合は下がって,和書の割合が上がっている。ニューメディアや視聴覚資料の購入費が含まれる「その他」の割合が和雑誌を追い越している。数字だけをみれば,洋書の購入費がニューメディアや視聴覚資料にシフトしているといえる。
| 和書単価 (円) | 4,700 | 4,900 | 5,500 | 104% | 117% | |||
| 洋書単価 (円) | 9,900 | 10,100 | 9,700 | 102% | 98% | |||
| 和雑誌単価 (円) | 16,200 | 17,300 | 18,600 | 107% | 115% | |||
| 洋雑誌単価 (円) | 42,600 | 44,600 | 47,600 | 105% | 112% | |||
| 和書 (億円) | 148 | 174 | 211 | 118% | 143% | 28% | 28% | 30% |
| 洋書 (億円) | 160 | 176 | 160 | 110% | 100% | 30% | 28% | 23% |
| 和雑誌 (億円) | 37 | 48 | 57 | 129% | 155% | 7% | 8% | 8% |
| 洋雑誌 (億円) | 141 | 177 | 198 | 126% | 140% | 27% | 28% | 28% |
| その他 (億円) | 27 | 39 | 63 | 148% | 235% | 5% | 6% | 9% |
| 総資料費 (億円) | 524 | 628 | 701 | 120% | 134% | 100% | 100% | 100% |
| 和書 (万冊) | 314 | 355 | 383 | 113% | 122% | |||
| 洋書 (万冊) | 162 | 174 | 165 | 107% | 102% | |||
| 和雑誌 (万点) | 23 | 28 | 31 | 122% | 135% | |||
| 洋雑誌 (万点) | 33 | 40 | 42 | 121% | 127% | |||
| 大学数 (校) | 460 | 507 | 565 | 110% | 111% | |||
【表1:大学図書館の資料費と資料点数(1985-95)】(9)
公共図書館における外国資料の購入費は、多くても資料費の1%〜2%である。公共図書館で購入される外国資料は,日本関係書,ベストセラー,文芸書,絵本,児童書,地図,ガイドブック,ビジュアル書,美術書,写真集,参考資料などである。公共図書館では,近年,多文化社会に対応して英語以外の外国資料の購入(10)が活発になりつつある。日本で暮らす外国人の数が,韓国・北朝鮮,中国,ブラジル,フィリピン,アメリカの順で,東南アジアの国からの外国人が多いことや,在日外国人への図書館サービスについての言及(11)もある。
購入する資料の選定を行い,書誌事項や価格などの調査を済ませた後,資料の価格,資料の入手先の提供するサービス,図書館の設置母体の会計規則,この3つのバランスを考慮して資料の発注先を選択する。先に述べたように外国資料の流通経路は3つあるが,外国図書を扱う書店から購入する方法が図書館では一般的である。資料の選択,発注,納品,支払,督促などの日常的な購入手続きは,和書の場合とおなじである。
図書の選択には,外国書専門書店の作成する販売目録や海外出版者の新刊案内,在庫目録がよく使われる。出版情報誌,雑誌の書評欄,書評紙なども利用される。
図書館における大半の資料の発注先は,長年の取引関係から数社の特定の書店に固定されていて,日常業務では,そのうちのどこに発注するのかを決定する。図書館は大口顧客として店頭小売価格から値引された価格で図書を購入している。商品情報などの専門的サービスより値引きを優先させることは控えるべきである。発注は図書一点ごとに個別の複写式発注様式を使用すると,単品管理が可能になり,その後の処理に柔軟性を持たせることができる。書店と図書館全体の事務処理の簡略化につながるような標準化された発注様式の作成も考慮されるべきである。
書店の請求から図書館の設置母体による実際の支払までには数ヶ月を要する。図書館員は,設置母体内の会計処理手順にも気を配ってできるだけ早い支払が行われるよう配慮すれば,書店との良好な関係を築くこともできる。限られた資本の零細な外国書専門書店にたいしては,特に早期支払を心がけたい。
納入が遅れている場合,図書館は資料を発注した書店にたいして督促を行う。書店からは,書店・取次での品切(OS: out of stock),出版者での品切・絶版(OP: out of print),未刊(NYP: not yet published)などの連絡がとどけられる。必要に応じて,解約,別書店への手配などが図書館では行われる。
一般的にいって,先進諸国の外国資料には以下のような特徴がある。
外国書専門書店を通さないで,図書館が海外出版者・取次やそれらの日本事務所へ直接発注する方法も可能であり,いくつかの事例が報告(13)-(15)されている。直接発注により,通常は外国書専門書店に図書館が支払う数料を節約でき,特に円高の際には輸入における円高差益を図書館が直接享受できる。同じ予算でより多くの資料が購入でき,さらに,外国資料の出版流通事情にも詳しくなれる。反面,外国語での発注,クレーム処理,海外の商習慣への対応,送金手数料などの諸経費の負担など,外国書専門書店の機能を図書館が果たすために担当者の負担が増える。
図書館経費削減への有効な対応策として直接購読を位置づけることも一つの選択であるが,外国書専門書店をうまく使って図書館本来の仕事に集中することが本筋であろう。しかし,情報通信技術や標準化技術(16)が発達することによって,仲介業者としての外国書専門書店の役割が薄れて,生産者と消費者の直接取引が急速に身近なものになってくる(17)ことも今後は考えられる。
最初に「雑誌」について簡単に説明する。逐次刊行物(serial)は,新聞,雑誌,年鑑などを包括する呼称である。定期刊行物(periodicals)は,逐次刊行物から刊行間隔の短い新聞と,一年の総括を行うような刊行間隔の長い年鑑,白書などの刊行物をのぞいたものである。さらに,定期刊行物は,その内容や読者により一般的な読書のための雑誌(magazine)と,特に学術論文を掲載する学術雑誌(journal)に分けることができる。
雑誌は,同一のタイトルで継続して刊行される出版物で,複数の記事が掲載され,その内容に速報性がある。雑誌におけるこれらの特徴から,雑誌はいったん購入を開始したら,毎年、予算を確保して購入を続ける必要がある。この「継続」という特徴により,年10%にもなる大幅な価格上昇のある雑誌費は全資料費の大きな割合を占め続け,資料費を将来にわたって圧迫することになる。
外国雑誌の購入は,一般雑誌も,商業雑誌や学協会誌などの学術雑誌も,定期刊行物の予約を手配する「予約購読代理店」(以下,代理店)を経由して購入される。先に説明した大手や中堅の外国書専門書店は,購読代理店として予約購読業務を図書館にかわって行っている。
代理店を利用しない出版者からの直接購読の例はほとんど皆無で,図書館の外国雑誌の購入は代理店経由といってよい。後述する海外代理店の利用は近年増加している。外国雑誌の購入にあたっては,出版者側による予約購読の原則があり,以下の原則に従って雑誌購読の手続きが毎年繰り返される。
図書館,代理店,出版者には三角関係がある。図書館は,代理店との間で次年度購入契約し,料金を先払いする。代理店は,出版者への雑誌の注文と送金を代行して行う。出版者は,雑誌を毎号確実に図書館に送り届ける。
外国雑誌購読の年間スケジュールは概ね以下のようになスケジュールで行われる。7月頃から図書館は翌年に購読する追加・削除タイトルを決定する。8月頃から競争入札を行う図書館もある。9月には,図書館は翌年のタイトルを代理店に通知して価格を見積もる.そして,10月には,図書館と代理店は価格交渉を行った後,代理店は出版者への発注・送金を行い,図書館は代理店へ代金を支払う。予約購読料の支払時期については,私立大学では予約購読年の前年末までに予約購読料を代理店に支払うが,国の会計規則の関係で国立大学では予約購読年の当該年度になってから支払う。
海外代理店では,通常,秋に行われる契約・支払を春におこなう方法があり,この早期契約では3%程度の割引がある。しかし,金利の低い日本においては、国内代理店はこのようなサービスを行っていない。
国の契約制度には一般競争契約,指名競争契約,随意契約の三種類の方法があり,図書館の資料購入にあたって,従来は随意契約がとられていた。しかし,90年代は競争原理の導入による競争入札も実施されるようになり,代理店間の価格競争が激化している。
価格の算定方式には,係数方式,CPレス方式,個別タイトル方式の3つがある。係数方式は,外国資料の外貨とその通貨の実勢レートに手数料を加算した係数とを掛け合わせて購入価格とする。CPレス方式は,代理店のカタログの円定価に一定の値引き率を掛け合わせて購入価格とする。個別タイトル方式は,個々のタイトルの特性(価格帯,出版者,出版国,通貨,刊行回数,取引条件)を考慮してタイトル毎に手数料を算定する方法である。
外国資料の出版情報を調査するための出版物を使って,図書館では購入する資料を選択し,発注のための書誌事項を確認する。それらのトゥールには,さまざまな全国書誌,販売目録,総合目録などがある。ここでは,英語圏の代表的な販売目録と,出版情報の専門雑誌などを紹介する。
Books in print. Bowker 年刊:入手できる米国の図書を収録している。
Publishers weekly : the American book trade journal. Bowker 週刊:米国の出版情報誌で,米国で出版される新刊図書リストも載せている。
Whitaker's books in print. Whitaker 年刊:入手できる英国の図書を収録している。
Bookseller : the organ of the book trade. Whitaker 週刊:英国の出版情報誌で,英国で出版される新刊図書リストも載せている。
Ulrich's International Periodicals Directory. Bowker 年刊:国際的に最もよく使われている雑誌の販売目録である。世界の雑誌16万タイトルを収録している。969の主題によって配列されていて,廃刊・休刊中のリスト,アルファベット順索引,ISSN索引をもつ。出版者の住所,発行部数,広告書評欄の有無,内容,その雑誌を収録対象にしている二次資料名,通巻索引の有無も記載されている。1996年版は,5分冊1万ページである。不定期刊行物やモノグラフシリーズを収録していたIrregular serials and annuals :an international directory. 1st ed. (1967)-13th ed. (1987/88)を吸収している。
むすびめの会編『多文化社会図書館サービスのための世界の新聞ガイド--アジア・アフリカ・中南米・環太平洋を知るには』日本図書館協会 1995.12 232p:図書館と在住外国人をむすぶ「むすびめの会」が767紙を紹介している。その国と新聞の概要,国内での入手先と価格などが記載されている。1面の写真がのせられており,その新聞の雰囲気を伝えている。国内で発行されている在日外国人向けの新聞のリストと関連団体の名簿が資料としてつけられていて,多文化サービスの包括的なガイドとしても利用できる。
The Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists. Association of Research Libraries 年刊:1996年の第6版には,ネットワーク上で流通する電子雑誌1,688タイトル,ディスカッションリスト3,000タイトルが収録されている。1995年より26%増,電子雑誌は257%増である。図書館と図書や雑誌についての情報収集に役立つ電子雑誌も収録されている。
Serials. UKSIG 季刊:英国の雑誌研究・情報誌で,米国の情報にも詳しい。
Newsletter on serials pricing issues.(ISSN 1046-3410) Editor: Marcia Tuttle 月数回刊:インターネットで入手できる雑誌の価格問題に関する電子雑誌である。<URL:http://www.lib.unc.edu/prices/>
60年〜70年代の関心事は未着欠号問題(20)であった。輸送途中での事故が発生しやすい船便から,比較的安価で航空便とほぼ同じスピードで届くエアカーゴの導入(21)や,90年代のチェックイン方式(22)による代理店段階での欠号補充によって,欠号問題は大幅に改善された。
70年後半〜80年代は,固定為替相場制から変動為替相場制への移行(71年)による混乱、オイルショック(73年〜74年)による紙の価格の急騰があった。円切り上げの外国資料価格への反映の遅れと,オイルショックによる雑誌価格の急上昇などから,これ以降、価格問題が大きな関心事になっていく。さらに、代理店が出版者と輸入総代理店契約(23)を結び、特定出版者の雑誌について割高な円建て価格が設定され,図書館側からの反発を招いている。日本支社を構えた外資系の海外代理店(82年に2社)は,豊富な商品情報と低価格が評価されたものの、定期的に代理店の営業担当が図書館を訪問する(書籍の販売も行っている関係で図書館を訪問する機会が多い)などの日本的商習慣に阻まれ,少数の私立大学図書館が採用するにとどまった。しかし,80年代後半から90年代に入り,前年度払いのできない国立大学の会計方式にあわせた受注を始めたことや、国立大学の競争原理の導入により、海外代理店は国立大学図書館にも多く採用されるようになった。国内代理店は海外代理店に現実的な驚異を感じ,手数料の引き下げやチェックイン方式の開始など,価格面やサービス面で多くの改善を行った。海外への直接発注もこの頃から報告され始めた。価格上昇に予算増加が追いつかないため、自然科学系図書館と外国資料の比率の大きい国立大学図書館では,購入外国雑誌のタイトル削減がおこなわれはじめた。
90年代は、80年代の様々な価格問題とシステム化された流通機構の改善がさらに進行している。次に、それらを価格問題として概要を説明する。
資料購入費が伸びない図書館にとって,外国資料のうちで特に学術雑誌の価格上昇は大きな悩みとなっている。価格問題は、円高で雑誌価格の上昇が相殺されている間は大きな問題にならないが、円安になると雑誌価格の上昇と円安のダブルパンチとなって急浮上する。学術雑誌の価格上昇の要因は,社会・経済,出版者,代理店,図書館に整理できる。
| 社会・経済 | 為替レートの変動 | 雑誌価格の不規則な変動 |
| 物価上昇 | 雑誌価格の緩やかな上昇 | |
| 出版者 | 投稿論文の増加によるページ数の増加 | 雑誌価格の大幅な上昇 |
| 価格戦略,出版・販売戦略 | 差別価格,寡占化 | |
| 代理店 | チェックイン方式などの付加価値サービス:フロッピー納品,発注・納品データの代行入力 | 取扱手数料の上昇,アウトソーシング(28) |
| 海外代理店や他業種の進出による価格競争の激化 | 寡占化,公取調査(29)-(30) | |
| 図書館 | 予算難からの購読中止による購読者数の減少(31) | 学術文化へ影響 |
| 文献複写への依存 | 出版者の販売戦略への影響 |
【表2:学術雑誌の価格上昇要因と問題点】
世間でよく取り上げられる価格問題は,内外価格差(32)と円高差益の還元(33)-(34)である。輸出主体の企業では,おなじ商品でも所得水準の高い国では高く,他の国では安くするというふうに,その国の所得水準や需要を考慮して,利益が極大になるような価格戦略が普通におこなわれている。国内では儲からないので海外で儲けるとか,国内で儲けた分で海外で安く販売してシェアを拡大し,独占的な市場を獲得した後は価格を支配できるとか,生産者側の価格戦略による内外価格差がある。これが差別価格である。経済の側面からみれば,外国資料もコンピュータや自動車と同様の輸出商品にすぎないのである。しかし,IFLAや日本の図書館団体の努力(35)によりアメリカや日本にたいする差別価格の多くは解消された。このように,世界中の価格情報が伝わりやすくなっている現在は,供給側だけの理論による価格戦略は維持できなくなりつつある。
また,輸入業者である代理店が円高差益を自分だけの利益として,顧客に円高差益が還元されていないという指摘もされている。現地価格での調達ができれば差別価格の回避と円高差益の享受が可能で,そのための方策としては海外代理店の利用と図書館の直接購入がある。円高は世界経済の情勢に左右される不測の要因であり,円安に振れたときのリスクを常に伴っている。
97年の時点で、ある大手の外国書専門書店では受注される外国図書の7割がネットワークを使って発注(36)-(37)される。発注から納品まで最短で1週間,平均すると北米で20日,欧州で30日という実績である。外国書専門書店では,機械化以前は1タイトル毎の加除式の台帳によって発注情報がコントロールされていたが,発注の機械化が80年半ばにはじまり,オンライン発注は90年前半に開始されている。図書館の機械化と同時進行していた格好である。
外国雑誌に関しても,90年代になって国内代理店も海外代理店にならって、出版者から図書館に直送する方法を改めたチェックイン方式の提供を開始した。これは、いったん国内外の代理店の集荷基地に雑誌を集めて、集荷基地で受付チェックを行い,出版者に対する欠号請求を済ませてから、個々の図書館への雑誌をまとめて宅配するシステムである。図書館は受付チェックのデータをフロッピーなどの電子媒体で図書館システムに取り込むことにより、自館での受付業務を簡略(もしくは省略)でき、欠号の発生が減少し、欠号の補充も改善される。チェックイン方式により,図書館業務のテクニカルな部分を外部委託し、不足しがちなマンパワーをより生産性の高いサービス部門や企画部門に振り向けることが可能になる。
体力のない外国書専門書店は激化する価格競争に追随できない。機械化とネットワーク化に投資できない書店は,経費削減や納期の短縮に対応できない。顧客は安くて早い大手の書店に発注を集中させる。かくて大手代理店による寡占化が進行する。しかし,システムにのりにくい入手困難な外国資料は取り扱いを敬遠される傾向もある。この辺りに中小代理店の活路があるといえる。
また,出版者は売上の伸び悩む従来の紙媒体での出版と平行して,新しい収入源の一つになりうる電子出版の可能性を探り始めている。そのため,図書館でも電子形態の資料への対応(38)-(39)のために、予算や人員の手当が必要になる。予算難、人員難の時代に向かって、図書館も外国書専門書店も情報の仲介業者であるとの認識(40)にたって、お互いが協力して困難に立ち向かっていきたいものである。
1:根本彰 日米比較を通してみる出版流通と図書館との関係 『図書館情報大学研究報告』 Vol.8, no.2(1989) p1-17
2:海外の状況 <日本図書館協会出版流通対策委員会編 『図書館と出版流通に関する資料集』 日本図書館協会 1981.10 286p (図書館と出版流通 第1集)> p86-131
3: 公正取引委員会事務局取引部取引課編 『主要国における出版物の流通実態調査』公正取引協会 1979.6 130p
4:窪田輝蔵 4-2 学術情報:先進諸国における出版と流通--米英を中心として『図書館研究シリーズ』 No.30(1993.3)p418-459
5:交換レートからむ特異な流通 <村上信明 『出版流通図鑑』 新文化通信社 1988> p.330-339
6:洋書問題研究会 岐路に立つ洋書業界 『出版レポート』 No.34(1997.6) p46-53
7:武塙修 出版物販売額の実態と分析『出版ニュース』 1778号(1997.9/中)p8-11
8:出版物輸入額統計表・1996年 <『出版年鑑 資料・名簿』 出版ニュース社 1997.5> p336-337
9:文部省『大学図書館実態調査結果報告』年刊
10:竹内紀吉 市立図書館の洋書(外国書)収集--県立,国会,大学とのネットワークのなかで 『図書館雑誌』 83巻2号(1989.2) p62-63
11:『図書館はいま--白書 日本の図書館 1997--』 日本図書館協会 1997.3 外国人のために(p16-17),多文化サービスへの取り組み(p137-138)
12:S・フォード著; 丸谷洽一, 高木由美子訳 『図書館資料の受入 プランニングから集中整理まで』 勁草書房 1984.6 298p (Ford, Stephen. The acquisition of library materials. Rev ed. ALA, 1978)
13:森茜,大場高志 外国図書の海外直接購入について--国立大学図書館における一方法 『大学図書館研究』 No.37 (1991.3) p44-52
14:渡辺克己 海外発注方式のメリット--上智大学の事例 『図書館雑誌』 32巻 5号(1989.2) p68-69
15:戸田慎一 インターネットによる洋書購入 『専門図書館』No.158(1996)p16-24
16:松平直壽 『コードが変える出版流通 : ISBNのすべて』 日本エディタースクール出版部 1995.3 148p (巻末付録:The ISBN system user's manual. International ISBN Agency, Berlin, 1986)
17:Frank R. Bridge. Connecting library automated systems to the business world. Library journal. Vol.119, no.4(1994.3.1) p38-40
18:長谷川豊祐 大学図書館における外国雑誌の購入について 『専門図書館』No.158(1996) p25-31
19:長谷川豊祐 外国雑誌の価格問題--文献紹介と20年間の動向-- 『[私立大学図書館協会東地区研究部会研究部]逐次刊行物研究分科会報告』No.51(1993.12) p6-31
20:岩本博 外国雑誌購入上の諸問題 『医学図書館』 24巻3号(1977.9) p123-141
21:岩本博 外国雑誌流通上におけるエアー・カーゴ・サービスの現状と役割 『医学図書館』 27巻2号(1980.6) p82-92
22:長谷川豊祐 外国雑誌の価格問題--国内代理店新方式の概要とその得失-- 『図書館雑誌』87巻9号(1993.9) p669-672
23:片山信子 もうひとつの差別価格--洋雑誌輸入総代理店制度を考える 『図書館雑誌』48巻2号(1990.2)p87-89
24:特集ジャーナルのコストパフォーマンス 『情報の科学と技術』47巻2号(1977)p57-93
25:ACCESS NEWS編集局編 『ACCESS NEWS Q&A 〜外国雑誌の基礎知識および実務〜』紀伊國屋 1996 76p
26:Cummings, A.M. et al. University libraries and scholarly communication : a study prepared for the Andrew W. Mellon Foundation. The Association of Research Libraries, 1992.11, 205p <URL:http://www.lib.virginia.edu/mellon/ mellon.html>
27:Brookfield, Karen ed. Scholarly communication and serials prices. Bowker 1991 155p.
28:佐々木克彦 企業図書館とアウトソーシング 『情報の科学と技術』47巻5号(1977)p238-244
29:大石博昭 「六大協」の外国雑誌価格協議打切りの報告--簡潔にして、重要な決定--. 大学の図書館. Vol.12, No.10 (1993.10)
30:石岡克俊 「手数料」に関する共同行為と競争の実質的制限--洋書輸入業者カルテル事件 『ジュリスト』No.1117(1997.8.1-15) p196-198
31:McCarthy, Paul. Serial killers: academic libraries respond to soaring costs. Library journal. Vol.119, no.11(1994.6.15) p41-44
32:工藤進 内外価格差とその背景 『世界』573号(1992.10) p312-320
33:渋川雅俊 洋書は安くなる!?--円切上げと洋書価格問題の推移 『KULIC』 No.4(1972.5) p21-24
34:”円高時代”における外国雑誌の購入 『図書館雑誌』 81巻10号(1987.10) p597-605
35:国公私立大学図書館協力委員会「差別価格問題」ワーキング・グループ 差別価格問題調査報告書--外国雑誌の差別価格の実態 『大学図書館研究』 No.39(1992.3) p.63-69
36:EDI特集 VINE. No.94 (1994.3) p.3-37
37:EDI特集 Library administration & management. Vol.10, no.3 (1996 Summer) p138-174
38:ACCESS NEWS編集局編 『ACCESS NEWS Q&A 〜学術雑誌を取り巻く電子化の状況〜』紀伊國屋 1996 76p
39:窪田輝蔵 電子ジャーナルと科学コミュニケーションのコスト 『医学図書館』43巻3号(1996) p308-314
40:David Brown. The future
of electronic information intermediaries : a survey undertaken
by DJB Associates on behalf of UKSG and JISC/ISSC. UKSG 1996.9
337p
↑
カットした参考文献
95◆Schauder, Don; 福島勲ほか訳 専門論文の電子化--大学研究者の態度と学術情報流通産業に対する意味(1)〜(3)
『情報管理』38巻1号(1995.4)p33-44,38巻2号(1995.5)p137-148,38巻3号(1995.6)233-245
[Schauder, Don. Electronic publishing of professional articles:
attitudes of academics and implications for the scholarly communication
industry. Journal of the American Society for Information Science.
Vol.45, no.2, p.73-100 (1994)の参考文献リストをのぞいた全訳]
97◆石岡克俊 「手数料」に関する共同行為と競争の実質的制限--洋書輸入業者カルテル事件
『ジュリスト』No.1117(1997.8.1-15) p196-198 「大学または図書館等の図書の購入は,予算消化という形で行われることも多く,価格面に関して必ずしも敏感ではない」
公正取引委員会
・価格協定強制捜査:1976.2-8
・6大協の洋雑誌の集団交渉:1988.6
・洋書輸入業者による外国新刊図書のマークアップ額決定(1995.3-1997.9):1995.3- 立入調査,1996.5.31 審決,1997.9.3 課徴金納付命令
95◆洋書の世界にも価格破壊の波 『AERA』8巻20号(1995.10.18)p70-71
96◆インターネットで販売システムを構築する法--インターネットを利用するよう書販売に成功した家電量販店のダイイチ.その次なる販売戦略は 『プレジデント』 34巻5号(1996.5)p70-77
96◆大学生協,インターネットで丸善の牙城に挑む 『日経ビジネス』 893号(1996.5.6)p12
80◆海外の本 : 洋書入門 / 図書新聞編集部編. -- (BN02948693) 東京 : 図書新聞, 1980.9. 226p ; 17cm -- 1981
68◆洋書入門 / 図書新聞編. -- (BN0943561X) 東京 : 図書新聞社, 1968. 176p ; 18cm
80◆海外出版の実務 : 国際共同出版の基礎知識 / 出川沙美雄著. -- (BN07382691) 東京 : 出版研究センター, 1980. 233p ; 19cm. -- (出版研究叢書)
72◆出版流通問題の国際比較 : 第7回海外出版販売専門視察団報告書 / 海外出版販売専門視察団 [編]. -- (BN0371185X) 東京 : 海外出版販売専門視察団, 1972. 327p ; 22cm
70◆情報化時代を戦う欧米の出版産業 : 第5回海外出版・販売専門視察団報告書. -- (BN06197876) 東京 : 日本出版販売, 1970.5. 5, 242 p. ; 25 cm
95◆出版文化産業ビジョン21 : 21世紀に向けて産業をどう変えるか. -- (BN13317934) 東京 : 出版文化産業振興財団, 1995.8. 267p ; 26cm 内容: 参考1:生涯学習振興部会中間報告 : 出版産業部分抜粋 / 産業構造審議会 ; 参考2.海外出版事情視察報告 : マルチメディア最先端国アメリカを行く
81◆全国高等教育機関図書館における資料選択・収書事務・書店〜図書館関係調査結果報告書 / 日本図書館協会出版流通対策委員会編. -- (BN01036246) 東京 : 日本図書館協会, 1981.11. 343p ; 26cm. -- (図書館と出版流通 / 日本図書館協会出版流通対策委員会編 ; 第2集)
77◆公共図書館における図書購入の現状 / 図書館問題研究会出版流通問題委員会編. -- (BN08027775) 東京 : 図書館問題研究会出版流通問題委員会, 1977. 43p ; 26cm. -- (図書館と出版流通問題 / 図書館問題研究会出版流通問題委員会編)
89◆根本彰. 日米比較を通してみる出版流通と図書館との関係. 図書館情報大学研究報告. Vol.8, no.2, p.1-17 (1989) ◆図書館の問題を出版流通の問題として捉える,あるいは出版流通の問題を図書館の問題として捉えることがなされていないのは,それぞれにおける抜きがたいプロフェッション中心主義および業界中心主義に帰することができよう.別々のものに見える施設としての図書館と産業としての出版流通は本質的にいかなる社会制度の二側面であるのかを探ることが必要である。出版は,知的文化的制度としての位置付けと資本主義社会における産業としての位置付けの2つの異なった性格付けを持ち,これが時として矛盾をきたす。また,出版流通と図書館の関係において,欧米などの図書館制度の確立している国と比べて,図書館制度の発達の遅れている我が国には独自の状況が存在する。1)日本人の間では図書を自分で購入して所蔵することが習慣として定着している 2)制度としての図書館の発達の遅れていることがそのことにさらに拍車をかけている。 3)そのかわりに出版流通システムがよく発達しており,書店がどこに行ってもあるのでたいていのものはそれで間に合う。 わが国では,英米において図書館が果たしている役割の一部を書店が果たしているともいえる。 ◆日米における,図書刊行点数比較,主題別点数比較,種類別点数・売上金額比較(一般,専門など),消費ルート(小売店,図書館など)の金額比較,図書館市場の比較,をおこなっている。 ◆日本における洋書の市場規模と館種別の金額比較:大学,公共,学校,専門(◆専門情報機関総覧,専門図書館協議会白書)
88◆図書館情報学ハンドブック. 丸善, 1988 (10)図書館への流通:図書館への納入は,和書は小売書店,洋書は洋書店が行っているが,見積請求の煩雑な手続き,見計らい送品,雑誌購読料金の長期間立替払い,目録カードの添付など,通常の書店サービスを越えたサービスを求められているのが現状である。そのため,洋書の場合のように,定価からの大幅な値上げが必要になったりもしている。(p.267) (13)外国における出版メディアの流通:日本の出版流通体制は世界で最も整備されているが,諸外国の出版流通システムはきわめて未分化である。
80◆東京地区国立大学図書館協議会. 外国資料流通問題検討会第一次報告. 1980.9, 26p. (付属資料のみ未見)
88◆国立大学図書館協議会 外国出版物購入価格問題調査研究班. 外国出版物購入価格問題調査研究班第一次報告. 1988.6, 42p. ◆P.14, 参考資料4):外国図書資料の流通形態
89◆国立大学図書館協議会 外国出版物購入価格問題調査研究班. 外国出版物の購入価格問題に関する調査研究報告書. 1989.6, 68p. 差別価格と総代理店物を調査。2.1 価格
91◆国公私立大学図書館協力委員会. 国公私立大学図書館協力委員会「差別価格問題」ワーキング・グループ調査報告書. 1991, 26,18p.
72◆図書館白書 / 日本図書館協会. -- (AN00361480) (昭47)-. -- 東京 鶴見大 1972-1980(1972-1980)
97◆訪問記. 1997.9.12 公共図書館の洋書購入状況(丸善 吉儀) 1997.9.10 丸善平和島にてMACS2見学・写真撮影 1997.9.17 日本橋の丸善第4ビルにて洋書の海外物流と国内流通 1997.9.22 ジプロ 根本氏にインタビュー
97◆川村光郎. 洋書業界雑記 空洞化も懸念されるインターネット書店. 新文化. No.2224, 1997.8.21
96◆洋書問題研究会. 学術文化の発展における大学図書館と洋書業界の役割. 1996.11.30 中央大学駿河台記念館 ◆川村光郎. 大学図書館と「洋書」店が消滅する前に. 8p. ◆洋書問題研究会報告(改訂2版) 1996年11月30日 12p.
96◆洋書問題研究会. 「学術文化の発展と洋書業界の役割」出席者の発言のメモ. 1996.6.22 11p. ◆洋書問題研究会報告 1996年6月22日 11p.
96◆洋書問題研究会. シンポジウム「学術文化の発展と洋書業界の役割」--京都集会--. 1996.10.12 4p. ◆洋書換算レート表 ◆洋書輸入業者一覧 1996 9p. ◆通関統計の推移 ◆経済成長率の推移
96◆Taylor, Sally. Kinokuniya in new approach to Japanese book imports[紀伊国屋書店の洋書輸入への新たな取り組み]. Publishers weekly. Sept. 16, 1996
93◆醍醐聰. やさしい経済学 バランスシートの内と外(4)円高差益はどこに. 朝日新聞. 1993.5.18 ◆石原隆良. (JBIA資料) 醍醐聰. やさしい経済学 バランスシートの内と外(4)円高差益はどこに を拝見して 10p.
92◆白書・日本の専門図書館1992. 専門図書館協議会, 1992.7, 378p.
89◆白書・日本の専門図書館1989. 専門図書館協議会, 1989.6, 452p.